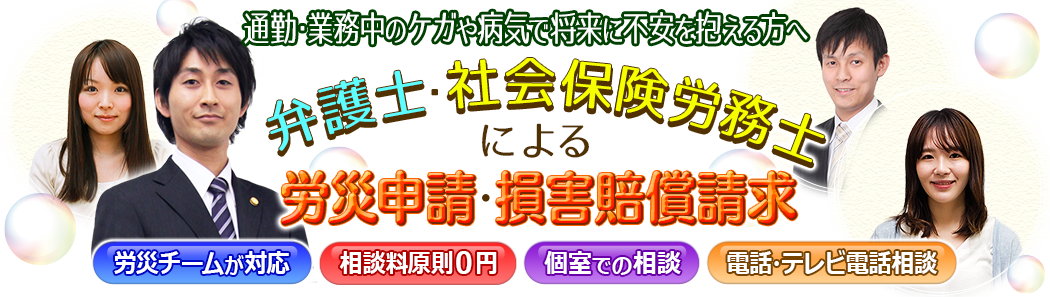
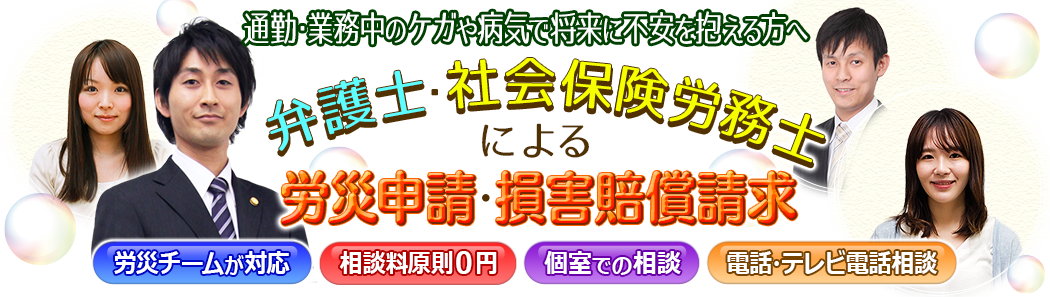
大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
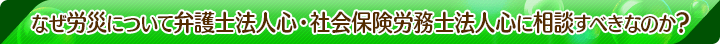
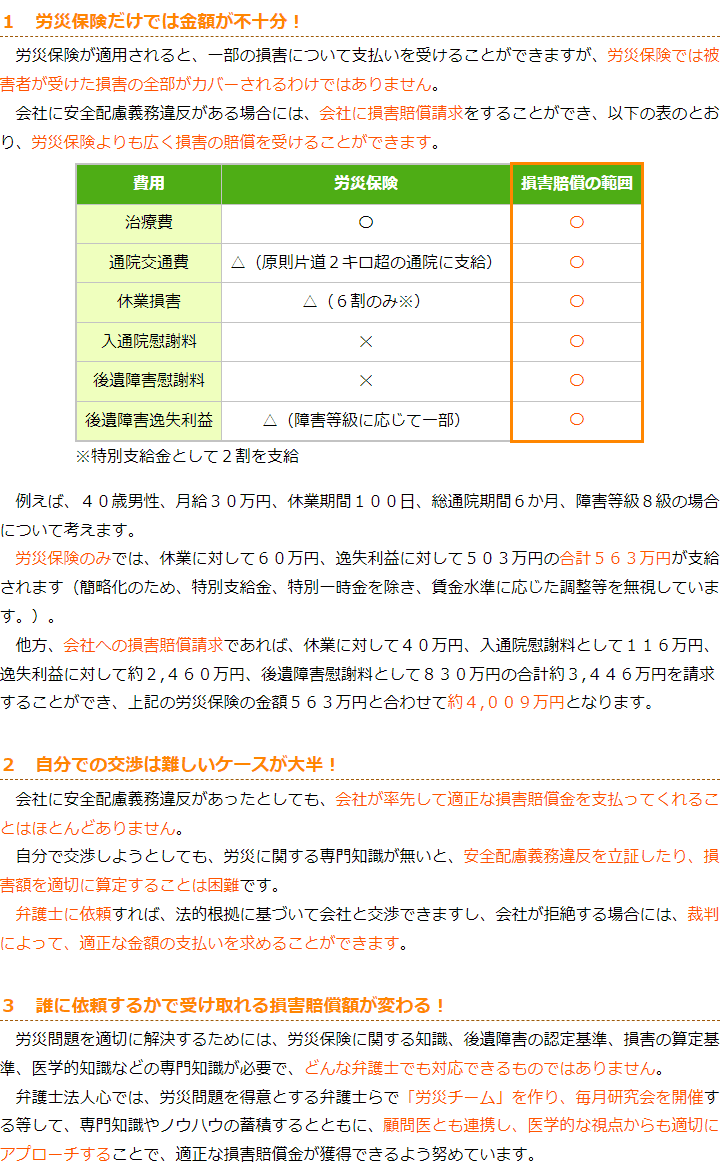
サイト内更新情報(Pick up)
2025年12月8日
労災のケガで通院しているのですが、転院はできますか?
労災のケガで通院している場合に、転院して違う病院に通院することはできます。転院する場合には、転院先の病院が、これまでの治療状況などを把握できるようにするため・・・
続きはこちら
2025年10月8日
職場での転倒事故で労災保険が利用できる要件や補償について
職場での転倒事故で、労災保険を利用するためには、業務災害にあたることが必要となります。業務災害にあたる、すなわち、「業務上」といえるかどうかの判断は、①業務・・・
続きはこちら
2025年8月14日
機械に巻き込まれて指を切断した場合の労災請求
業務中に指を切断する事故が発生した場合、速やかに会社に報告してください。また、当然のことですが、必ず病院を受診して治療を受けましょう。病院を受診するときは、・・・
続きはこちら
2025年6月9日
パートでも労災の休業補償は認められますか?
休業補償は、正規社員はもちろん、非正規社員の方でも雇用形態にかかわらず受け取ることができます。そのため、パートでも労災の休業補償は認められます。補償内容も・・・
続きはこちら
2025年4月9日
労働災害に遭った場合の慰謝料の請求
労災に遭った場合には、まずは速やかに会社に報告してください。報告が遅れると、会社から労災として扱ってもらえない場合があります。また、第三者の行為によってケガを・・・
続きはこちら
当事務所の最寄りの駅出口は、横浜駅のきた東口Aです。
きた東口Aへは、横浜駅きた通路・JR北改札からお越しいただくのが便利です。

階段やエスカレーター、エレベーターなどで、きた東口Aから駅の外に出てください。



橋を渡ったら、右方向にある道路をまっすぐ進んでください。

まっすぐ進むと、国道1号線と交差するT字路がありますので、そこを左折してください。
T字路を左折すると、ファミリーマート横浜駅東口店が見えます。

左折したら、国道一号線に沿ってまっすぐ進んでください。

一つ目の交差点から少し先、左手に横浜金港町ビルがあります。

ビルに入られましたら、エレベーターで7階の事務所までお越しください。


労災によってケガなどをし、治療終了後も一定の症状が残っている場合、後遺障害(障害補償給付)の申請を検討することになります。
労災の後遺障害の等級は、症状に応じて1級から14級まで規定されています。
例えば、両上肢をひじ関節以上で失った場合には1級、一下肢をひざ関節以上で失った場合には4級、一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失った場合には8級、一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残す場合には10級、一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残す場合には12級、局部に神経症状を残す場合には14級に該当することになります。
労災によるケガの治療が終了したとき(または症状固定と診断されたとき)、後遺障害の可能性がある場合には、後遺障害の申請を検討することになります。
後遺障害の申請を行う場合には、医師の診断書などと合わせて障害補償給付の請求書を労働基準監督署に提出します。
書類を提出した後、必要に応じて専門医による症状の確認が行われることがあり、その場合には労働基準監督署から案内があります。
労働基準監督署での審査の結果、後遺障害が認められた場合には、後遺障害等級に応じて年金または一時金が支給されます。
後遺障害等級が認められなかったり、認められた等級に不服がある場合には、審査請求という手続きによって不服を申し立てることができます。
労災事故にあった場合、どのような給付を得られるのか、そのための手続きはどうしたらいいのかなど、分からないことが多いと思います。
また、後遺障害の可能性がある場合の手続きについて、分からないことや不安に思うこともあるかと思います。
そのような場合は、当法人にご相談ください。
労災を得意とする弁護士が対応させていただきます。

労災にあった場合、会社や労働基準監督署に対してどのように対応すればよいか、申請できる給付の内容や手続きはどうなっているかなど、分からないことが多いと思います。
また、労災は、労働基準監督署で労災として認められているかどうか、通院中かどうか等によって、取るべき対応が変わるケースもあります。
このように、労災は、その時々の状況などをふまえた対応が必要となるため、労災について弁護士に相談する場合には、相談する弁護士を慎重に選ぶことをお勧めします。
弁護士法人心の特長として、以下のような点が挙げられると思います。
弁護士法人心には、元裁判官、元検察官、会社勤務経験のある者など、多様なバックグランドを持つ40名以上の弁護士が在籍しているほか、社労士資格を持っている弁護士もおります。
労災は、事故の内容によっては様々な観点からの検討が必要なケースもあるため(例えば、裁判を行う場合には裁判官の視点からの検討も必要になりますし、会社が刑事的責任を負うような事故の場合には刑事的観点からの検討も重要となります。)、多様なバックグランドを持った弁護士が多数在籍していることは、当法人の大きな強みであると思います。
弁護士法人心は、担当チーム制を取っており、労災については労災担当チームが事件を集中的に取り扱っております。
また、ご依頼いただいた案件は情報共有できるようにしているため、担当弁護士は、多数の他の事件を参考にすることができます。
弁護士法人心はこのような体制によって、労災に関する多くの知識、経験、ノウハウを蓄積しております。
弁護士法人心では、労災担当者が定期的に集って、事案の報告や検討、最新判例の動向や分析等行い、個々のスキルアップを図っております。
そして、このような研修や自己研鑽を通じて、労災事故をより適切に解決できるよう努めております。
以上のとおり、弁護士法人心当法人は、少しでも労災でお困りの方のお力になれるような体制をとるように努めております。
労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心当法人までご相談ください。

労働者が死亡したり、休業を必要とするような重大な労災事故が発生した場合には、通常、会社が労働基準監督署に労災の届出を行います。
仮に、会社が届出を行わない場合には、被害者自らが届け出ることもできるので、早めに労働基準監督署に相談しましょう。
労災保険から支給される主な給付には、①労災によってケガをしたり病気にかかったりして治療を受けたときに支給される療養(補償)給付、②労災によるケガや病気の療養のために働くことができず、賃金を受けられなかったときに支給される休業(補償)給付、③労災でのケガによって後遺障害が生じた場合に支給される障害(補償)給付、④労災によって労働者が亡くなったときに支給される遺族(補償)年金等があります。
労働基準監督署が被害者からの給付申請を認めない場合、障害給付申請に対して認定された後遺障害等級に納得がいかない場合などは、労働基準監督署の決定に対して不服を申し立てることができます。
この場合、決定通知を受け取ってから3か月以内に、その決定を行った労働基準監督署長を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して、「審査請求」という手続きを行います。
申請請求に対する決定にも不服がある場合は、決定から2か月以内に、労働保険審査会に対して、「再審査請求」という手続きを行います。
再審査請求に対する決定にも不服がある場合は、「取消訴訟」という行政裁判手続きを行うことになります。
労災の決定内容に納得がいかない場合は、不服を申し立てることができますが、具体的な手続き方法等、分からないことが多いかと思います。
労災などの案件を取り扱っている弁護士が対応させていただきますので、お困りのことがありましたら、当法人にご相談ください。

通勤災害は、労働者が通勤により負傷、疾病、障害または死亡した場合をいうとされています。
また、通勤とは、就業に関し、①住居と就業場所との間の往復、②就業場所から他の就業場所への移動、③住居と就業場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動、をいうとされています。
③は単身赴任などの場合に、単身赴任先住居と従来住んでいた住居との行き来も通勤として扱うという趣旨です。
通勤災害と認められるためには、移動が合理的な経路及び方法である必要があります。
そのため、通勤の途中で就業や通勤とは関係のない目的で合理的な経路をそれた場合(逸脱)や通勤の経路上で通勤と関係のない行為を行った場合(中断)は、原則、その後は通勤にはならないとされています。
ただし、日用品の購入、選挙権の行使など、厚生労働省令で定められた行為は、逸脱、中断の例外とされています。
このように通勤災害に関しては、細かい規定などもあるため、通勤災害にあたるかどうか分からない場合には、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
通勤中に労災事故にあった場合は、速やかに会社に報告するようにしましょう。
また、ケガがあった場合には、できるだけ早く病院を受診し、症状等をきちんと伝えるようにしてください。
会社への報告や病院での受診が遅れると、労災として認めてもらえなかったり、ケガと事故の間に因果家計はないと判断されたりすることがあるため注意が必要です。
そして、通勤災害として労災保険を利用する場合には、ご自身の会社に相談してみてください。
通勤災害が発生した場合、労災としての要件を満たしているか分からない、手続きなどが分からないということもあるかと思います。
そのような場合は、当法人にご相談ください。

通勤災害は、労働者が通勤により負傷、疾病、障害または死亡した場合をいうとされています。
また、通勤とは、就業に関し、①住居と就業場所との間の往復、②就業場所から他の就業場所への移動、③住居と就業場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動、をいうとされています。
③は単身赴任などの場合に、単身赴任先住居と従来住んでいた住居との行き来も通勤として扱うという趣旨です。
通勤災害と認められるためには、移動が合理的な経路及び方法である必要があります。
そのため、通勤の途中で就業や通勤とは関係のない目的で合理的な経路をそれた場合(逸脱)や通勤の経路上で通勤と関係のない行為を行った場合(中断)は、原則、その後は通勤にはならないとされています。
ただし、日用品の購入、選挙権の行使など、厚生労働省令で定められた行為は、逸脱、中断の例外とされています。
このように通勤災害に関しては、細かい規定などもあるため、通勤災害にあたるかどうか分からない場合には、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
業務災害は、労働者が業務上で負傷、疾病、障害または死亡した場合をいうとされています。
業務災害が認められるためには、労働者が労働契約のもとに事業者の支配下にあったときに生じたこと(これを「業務遂行性」といいます)、業務と傷病との間に相当因果関係が認められること(これを「業務起因性」といいます)が必要となります。
業務災害については、業務遂行性や業務起因性の有無が争いになることも多いため、弁護士に相談することをお勧めします。
通勤災害や業務災害が発生した場合、労災としての要件を満たしているか判断が難しいケースもあるかと思います。
当法人は、労災担当チームが労災事件を集中的に扱っており、多くの経験、ノウハウを蓄積しています。
労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

業務中に事故に遭ってしまった方、通勤途中や帰宅途中に交通事故に遭ってしまった方は、労災保険給付を受けるためには、労災保険給付の申請が必要となります。
その前提として、まず勤務先に労災事故の発生を届け出る必要があります。
労災保険給付の申請は、被災労働者自らが行うか、被災労働者が亡くなっている場合には遺族の方が代わりに申請をすることができますし、勤務先も代わりに手続きをしてくれます。
治療を続けていても、これ以上の症状の改善が見込めないといった症状固定の状態になり、一定程度以上の障害が残ってしまった方は、後遺障害等級認定の請求をしていくことになります。
この段階では、まずは弁護士が一度、後遺障害の程度を検討し、どのような資料を集めれば適切な後遺障害の等級が認定されるかを精査します。
資料を集めて、労働基準監督署長に提出します。
無事に後遺障害の等級が認定されれば、障害(補償)給付等の保険金を受け取ることができます。
もし、認定された等級に不服がある場合には、審査請求を検討していくことになります。
業務中の事故であれば、安全配慮義務違反が認められる場合には勤務先等への損害賠償請求をしていくことになります。
通勤災害などの交通事故である場合には、加害者側の保険会社等に損害賠償請求をしていきます。
示談交渉で満足のいく金額になれば示談でまとめますが、示談段階で納得のいく金額にならなかった場合には、訴訟をすることになります。
労災保険給付では慰謝料まではもらえませんので、「慰謝料」を賠償してもらうためには、勤務先や加害者に請求していく必要があります。
慰謝料だけでなく、「逸失利益」についても、労災保険給付だけでは不足している場合が多いため、必ず、一度は弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

労災が発生した場合は、まず会社に報告してください。
会社への報告を行わないと、けがや病気が別の原因で起こったと受け取られかねません。
また、けがや病気が生じている場合は、必ず病院を受診しましょう。
病院を受診していないと、後日、労災によってけがや病気が生じたことを証明することが難しくなってしまうので注意が必要です。
第三者の行為によってけがをしたような場合には、警察への届け出も行うようにしてください。
労災が発生したことを会社に報告したにもかかわらず、会社が労災として扱ってくれない場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
労働基準監督署に相談する場合は、労災に関する資料を持っていくと、説明や手続きをスムーズに行えると思います。
また、会社の対応などに疑問がある場合には、労災に詳しい弁護士に相談することによって適切なアドバイスを受けられることもあるので、弁護士に相談してみるのもよいと思います。
労災が認められ、労災で治療を受けている場合、治療終了後に後遺障害の申請を行うか、休業補償は十分に支払われているか、慰謝料の請求をどうするかなどを検討する必要があります。
そこで、労災で治療中に、これらの内容について、労災に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
事前に弁護士に相談することによって、治療終了後の対応や方針をあらかじめ検討することができ、速やかに次の手続きを進めることができると思います。
労災が発生した場合、会社や労働基準監督署への対応で分からないことや不安に思うことが出てくる場合もあるかと思いますし、労災で受けられる給付の内容など、疑問点も出てくるかと思います。
そのような場合は、まずは一度当法人にご相談ください。
当法人は労災のご相談を承っており、相談に対応させていただく弁護士は、労災事件などを中心に扱っている弁護士です。
労災のことなら当法人にお任せください。

労災申請を行う際は、気をつけておくべきポイントがあります。
例えば、時効となってしまう時期は、いつまでに請求すべきかを確認する上で重要です。
その他にも、休業(補償)給付における注意点や、労災事故発生報告書の作成における注意点などもあります。
以下にて、それぞれの注意点についてご説明いたします。
労災保険は、保険給付ごとに時効が定められています。
例えば、治療費にあたる療養(補償)給付(療養の費用に支給に係るもののみ)については、「療養の費用を支払った日ごとにその翌日から」(起算日)2年間で時効となってしまいます。
休業(補償)給付については、「労働不能の日ごとにその翌日から」(起算日)2年で時効となってしまいます。
例えば、Aさんが、今から3年前に当時の上司によるパワハラが原因でうつ病にかかってしまい、その後、会社を休職し、通院を続けていたとします。
しかし、これまでに労災保険給付の申請手続きはしていませんでした。
この場合、Aさんは、今までに支払ったうつ病の治療のための治療費や会社を休んだ分の休業補償について、すべて労災保険で補償してもらえるでしょうか。
この事例ですと、直近2年分に支払った治療費と、休業分については、療養(補償)給付と休業(補償)給付を受けることができますが、2年より前の期間に支払った治療費や休業分については、労災保険金の支払いが受けられないということになります。
休業(補償)給付については、休業初日から3日目までは、「待機期間」といって、労災保険からの給付は行われません。
業務災害の場合は事業主に休業初日から3日目までの休業補償をしてもらい、通勤災害の場合には、加害者に休業損害を請求する必要があります。
労災事故については、発生報告書を作成する必要があります。
ご自分で作成するのならまだいいのですが、会社任せにしてしまうと、会社に不利な事情をごまかされて記載されるリスクもあるかもしれません。
そうなれば、後日、会社に安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求をしたときに、労災事故発生報告書の記載を裁判所が重視した場合には、事実と異なる事実認定がされてしまうおそれがあります。
ですので、労災事故報告書などの、事故発生の状況説明については、提出される前に、必ず一度は目を通して、事実と異なる点がないかなどをチェックする必要があります。

社労士(社会保険労務士)の業務内容は、社会保険労務士法で定められています。
労災に関しては、以下のことが行えることになっています。
このように、社労士は、労災に関する申請手続きなどを行うことはできますが、会社や加害者に対する損害賠償請求などの交渉、裁判手続きは行うことができません。
弁護士の職務は弁護士法で定められており、訴訟事件、非訟事件、審査請求などの行政庁に対する不服申立て事件、一般の法律事務などを行うことができます。
ここでいう法律事務には、社会保険労務士の業務も含まれます。
そのため、弁護士は、労災に関する申請手続きはもちろん、会社や加害者との交渉、裁判手続きなども行うことができます。
社労士の中にも、労災案件を扱っており、労災について一定の知識を持っている方はいると思います。
労災の申請手続きを行うだけであれば、そのような方に相談することも選択肢になるかもしれません。
しかしながら、社労士は会社や加害者と交渉することができないため、会社や加害者に対して損害賠償請求を検討する必要がある事案の場合等、状況によっては弁護士に相談した方がよいでしょう。
例えば、安全面の配慮が不足している状況下で起こった業務災害や、第三者の行為によって生じた通勤災害のようなケースが考えられます。
弁護士であれば、労基署への労災申請手続き、労基署から労災に関する支給を受けた後の対応に関する相談など、段階に応じて相談をすることができますし、労災による治療終了後に会社や相手方との交渉、場合によっては裁判手続きを任せることもできるため、状況に応じた対応が可能になります。
労災に遭った場合、会社や労働基準監督署への対応、申請できる給付の内容や手続きなど、分からないことが多いと思います。
また、会社側の対応が適切なのか判断できないこともあるかと思います。
当法人は、労災チームが労災事件を集中的に扱っており、多くの経験、ノウハウを蓄積しています。
労災でお困りの方は、どうぞ当法人までご相談ください。

労災が発生した場合は、まず会社に速やかに報告してください。
また、第三者の行為によって負傷したような場合には、労災の発生状況を客観的に記録するために、警察への届出もしましょう。
会社への報告や警察への届出が遅れたり、報告や届出を行わなかったりすると、後日、労災の発生そのものを証明できなくなるケースもあるため注意が必要です。
また、労災によってケガをしている場合には、必ず病院で受診してください。
病院で受診するときは、カルテに残してもらえるよう労災発生時の状況等も説明するようにしましょう。
労働者が死亡したり、休業を必要としたりするような重大な労災事故が発生した場合には、通常、会社が労働基準監督署に労災の届出を行います。
仮に、会社が届出を行わない場合には、被害者自らが届け出ることもできるので、早めに労働基準監督署に相談しましょう。
労災によるケガの治療を受けたり休業したりした場合、労働基準監督署に申請することによって、療養や休業に関する給付を受けることができます。
労災に遭った場合に、労災保険から支給される給付としては、主に以下の4つがあります。
①労災によってケガをしたり病気にかかったりして治療を受けたときに支給される療養(補償)給付
②労災によるケガや病気の療養のために働くことができず、賃金を受けられなかったときに支給される休業(補償)給付
③労災でのケガによって後遺障害が生じた場合に支給される障害(補償)給付
④労災によって労働者が亡くなったときに支給される遺族(補償)年金
また、労災の内容等によってはその他の給付の支給を受けられる場合もあります。
申請のための用紙は厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。
参考リンク:厚生労働省・主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)
なお、申請のための様式は、業務災害と通勤災害とで異なるので注意してください。
労災に遭った場合、会社や労働基準監督署への対応、申請できる給付の内容や手続きなど、分からないことも多いと思います。
弁護士にご依頼いただくことで、そのような労災に関する手続きをサポートすることができます。
労災に遭うのが初めてで、何から始めればいいのか分からないという方もいらっしゃるかと思います。
当法人には労災のお悩み解決を得意としている弁護士がおりますので、まずはお気軽にご相談ください。

労災が発生した場合、まずは会社(事業者)に速やかに報告しましょう。
状況によっては、警察への届出も行ってください。
また、当然のことですが、必ず病院を受診しましょう。
病院を受診するときは、カルテに残してもらえるよう事故時の状況なども説明するようにしてください。
労災が発生したときは、基本的には会社が労働基準監督署に届け出ることが多いです。
しかし、場合によっては会社が対応してくれないケースもあります。
そのようなときは、被害者自ら届け出ることができますので、労働基準監督署に相談することをおすすめします。
労災によるケガの治療を受けたり休業したりした場合、労働基準監督署に申請することによって、療養(補償)給付や休業(補償)給付を受けることができます。
また、労災によるケガの治療が終了し(または症状固定と診断され)、後遺障害の申請をする場合には、医師の診断書などと合わせて障害(補償)給付の請求書を労働基準監督署に提出します。
後遺障害が認められた場合には、後遺障害等級に応じて年金または一時金が支給されます。
上記のように、労災にあった場合、労働基準監督署に申請して認められれば、療養、休業、障害などに関する給付を受けることができます。
とはいえ、休業補償は給付基礎日額の80%(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)しか支給されないほか、入通院慰謝料などは支給されません。
そのため、通常、労災保険から支給されない損害については、事業者に対して損害賠償を請求することになります。
事業者との話し合いによって解決できれば一番ですが、損害額などで折り合いがつかない場合には、裁判手続きも含めて対応を検討することになります。
どのような項目について損害賠償請求できるか等は、労災の案件を取り扱っている弁護士に相談することをおすすめします。

労災に遭われた場合、「会社にはどのように対応すればいいのか」「労働基準監督署への手続きは何をすればいいのか」「どのような補償が受けられるのか」など、様々な場面で分からないことが出てくる方もいらっしゃるかと思います。
労災は、ケースに応じて取るべき対応が変わることもあるため、労災に詳しくない弁護士に相談してしまうと、適切なアドバイスを得られない可能性も否定できません。
弁護士に相談する前に、相談予定の弁護士や法律事務所がどのような事件に力を入れているのか、労災事件を取り扱ったことがあるか等を調べた方がよいでしょう。
最近は、ホームページを公開している事務所も多く、インターネットなどで手軽に調べることができるので、相談する弁護士や法律事務所を決めるときの参考になるかと思います。
労災事件は、内容にもよりますが、労働基準監督署への手続き、会社とのやり取り等が必要となることが多いため、弁護士と相談しながら進めていくことが一般的です。
そのため、弁護士とのコミュニケーションがスムーズに行えるかどうかは重要なポイントになります。
そこで、労災について弁護士に依頼することを考えている場合には、依頼する前に、実際にその弁護士と直接話をしてみることをおすすめします。
また、実際に話をすることで、労災について詳しいかということもある程度知ることができるかと思います。
最近は、電話で相談できる事務所や、初回相談が無料の事務所もありますので、弁護士と直接話をしやすい環境になっているかと思います。
これらを利用して、相性の良さを確認することをおすすめします。
労災について弁護士に依頼する場合には、費用についてもきちんと確認することをおすすめします。
弁護士費用の料金体系は、弁護士や法律事務所によって様々で、依頼時に着手金が必要な料金体系を採用しているところもあれば、完全成功報酬型の料金体系を採用しているところもあります。
弁護士に依頼する前に、料金体系や見込まれる費用を確認することによって、最終的に負担すべき費用の見通しが立ちやすくなります。
上記のように無料相談を行っている場合は、その相談時に費用についても確認しておくと安心かと思います。
当法人は、労災担当チームが集中的に労災事件を扱っており、多くの事件を解決してきました。
また、横浜駅近くに事務所を構えているほか、お電話・テレビ電話での相談にも対応しています。
労災に関するご相談は原則無料でお受けし、被害者の方が相談しやすい環境を整えております。
横浜にお住まいで労災でお困りの方は、ぜひ当法人までご相談ください。

業務災害や通勤災害といった労災事故によって、重大な傷病を負ったり、後遺障害が生じたり、死亡してしまった場合、労災保険から年金が支給されます。
労災年金には、傷病(補償)年金、障害(補償)年金、遺族(補償)年金の3種類があります。
労災事故による負傷や疾病の療養開始後、1年6か月を経過した日またはその日以後、①その負傷または疾病が治っていない、かつ、②その負傷または疾病による障害の程度が傷病等級表の障害等級に該当する場合、傷病(補償)年金が支給されます。
傷病等級は1級から3級まであり、以下のように分かれています。
1級:神経系統の機能や精神に著しい障害を残し、常に介護を必要とするような場合
2級:神経系統の機能や精神に著しい障害を残し、随時介護を必要とするような場合
3級:神経系統の機能や精神に著しい障害を残し、常に労務に服することができないような場合
傷病(補償)年金は、この傷病等級に応じて以下のように支給されます。
傷病等級1級の場合は給付基礎日額の313日分
2級の場合は277日分
3級の場合は245日分
また、賞与などの特別給与を受けていた場合には、算定基礎日額に傷病等級に応じた日数分の傷病特別年金が支給されます。
算定基礎日額は、労災事故が発生した日または診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間に受けた特別給与の総額を365で割った額です。
労災事故によって後遺障害が生じ、後遺障害等級が1級から7級に該当する場合には、障害(補償)年金が支給されます。
障害(補償)年金は、後遺障害等級に応じて以下のように支給されます。
障害等級1級の場合は給付基礎日額の313日分
2級の場合は277日分
3級の場合は245日分
4級の場合は213日分
5級の場合は184日分
6級の場合は156日分
7級の場合は131日分
また、賞与などの特別給与を受けていた場合には、障害等級に応じた日数分の障害特別年金が支給されます。
なお、後遺障害等級が8級から14級の場合には、等級に応じた日数分の障害(補償)一時金が支給されます。
労災事故によって労働者が亡くなった場合、事故当時にその収入によって生計を維持していた配偶者等の遺族に対して、遺族(補償)年金が支給されます。
遺族(補償)年金は、遺族数に応じて支給されます。
遺族数が1人の場合には原則給付基礎日額の153日分
2人の場合は201日分
3人の場合は223日分
4人以上の場合は245日分
また、賞与などの特別給与を受けていた場合には、遺族数に応じた日数分の遺族特別年金が支給されます。

労災による損害の請求については、個々の状況に応じて、どこに対して、どのような請求を行うかを十分に検討することが重要になります。
労災に遭われた際は、労災保険からの補償を受ける他に、事業者等に損害賠償を請求することがあります。
どちらにも様々な項目がありますので、自分の場合はどの項目を請求することができるのか、参考にしていただければと思います。
業務災害や通勤災害といった労災に遭った場合に、労災保険から支給される主な給付の種類と概要は以下のとおりです。
労災が原因で負傷したり、病気にかかって療養を必要とするときに支給されます。
労災による負傷や病気の療養のため労働することができず、賃金を受けられないときに支給されます。
労災による傷病が症状固定した後に、障害等級1級から7級までに該当する障害が残ったときに支給されます。
労災による傷病が症状固定した後に、障害等級8級から14級までに該当する障害が残ったときに支給されます。
労災によって被災者が亡くなったときに支給されます。
労災によって亡くなられた方の葬儀を行うときに支給されます。
労災による治療開始から1年6か月経っても治らず、傷病等級が1級~3級に該当する場合に支給されます。
障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級の者と第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している者が、現に介護を受けている場合に支給されます。
労災の原因が、事業主の安全配慮義務違反や第三者の不法行為による場合には、事業主や第三者に対して、損害賠償請求を行うことが可能です。
その場合の主な項目と内容は以下のとおりです。
労災による傷病の治療のための費用
入院や通院のための交通費
入院中の生活や通院にあたって付添が必要な場合の費用
入院中の生活用品などの雑費の費用
傷病の治療のため働けないことによって生じる損害
入通院や死亡による精神的苦痛に対する損害
後遺障害や死亡により、将来得られたはずの収入が得られなくなったことに対する損害
具体的に受け取ることができる金額は、労災の発生状況、労災の原因、通院状況、後遺障害の有無等によって大きく変わります。
特に、後遺障害が認定された場合には、事業主や第三者に対して、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できることが多いため、弁護士へ相談することをおすすめします。
当法人では、労災担当チームが集中的に労災事件を扱っており、多くの解決事例を有しております。
横浜周辺で労災に遭いお困りの方は、お気軽にご相談ください。

労災とは、通勤中・業務中などに発生したケガや病気のことを指します。
労災に遭った場合には、労災保険から保険金の給付を受けることができます。
得られる給付には、休業期間の賃金を補償するものであったり、心身にケガが残って将来的な労働に支障が出てしまったことを補償するものであったりと、様々な種類のものがあります。
労災に遭って心身に負担がかかっている状態で、給付を受けるための申請手続を行うことは、大変なことです。
弁護士に依頼いただけば、申請の手続きを適切に、スムーズに進めるためのサポートをさせていただくことができます。
どのような書類をどのように用意すればよいのか等、丁寧にサポートさせていただきますので、ご安心ください。
労災の発生原因が会社側にある場合には、勤務先に損害賠償請求を行うことができます。
しかし、勤務先に対する損害賠償請求を個人の方が行ったとしても、適切な賠償を受けることは難しいと思われます。
弁護士に依頼いただければ、弁護士が被害者の方の代理人となって、勤務先への損害賠償請求を行うことができます。
適切な賠償金の獲得を目指し、法律や過去の裁判例などを元に交渉を進めますので、損害賠償請求をお考えの方は一度ご相談ください。
以上の通り、労災について弁護士に依頼いただくメリットは少なくありません。
横浜で労災についてお悩みの方も、当法人までご相談ください。
当事務所は横浜駅から徒歩3分の場所にありますので、来所いただく際も便利かと思います。